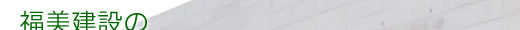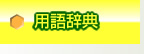お問い合わせ・お見積はもちろん無料です。お気軽にどうぞ。
●電話 052-325-8791 担当窓口 田口
●電話 052-325-8791 担当窓口 田口
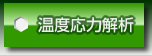
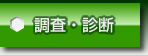


トップページ>コンクリート用語辞典
![]()
□ 有限要素法
有限要素法とは、対象になる物体を有限個の要素(三角形要素、四角形要素など)に分割して、それぞれの領域について力学的挙動を求める計算手法。
2次元、3次元解析に適用可能であり以下のような利点がある。
・任意形状の構造物に適用可能で、多様な境界条件を考慮できる。
・多くの分野で活用されており汎用的である。
・弾性解析において理論的根拠が明確で、解の信頼性も比較的高い。
2次元、3次元解析に適用可能であり以下のような利点がある。
・任意形状の構造物に適用可能で、多様な境界条件を考慮できる。
・多くの分野で活用されており汎用的である。
・弾性解析において理論的根拠が明確で、解の信頼性も比較的高い。
□ 有効ヤング係数
クリープひずみを温度応⼒解析に導⼊する⽅法で弾性係数を低減する形でクリープの影響を考慮する。
補正係数φ(t)・・・温度上昇時におけるクリープの影響を考慮するためのヤング係数の低減係数
最高温度に達する有効材齢までφ(t)=0.42
最高温度に達する有効材齢+1有効材(日)齢以φ(t)=0.65
最高温度に達する有効材齢後の1有効材齢(⽇)までは直線補間する。
補正係数φ(t)・・・温度上昇時におけるクリープの影響を考慮するためのヤング係数の低減係数
最高温度に達する有効材齢までφ(t)=0.42
最高温度に達する有効材齢+1有効材(日)齢以φ(t)=0.65
最高温度に達する有効材齢後の1有効材齢(⽇)までは直線補間する。
□ ひび割れ誘発目地
材料、配合等の対策によりひび割れを制御することが難しい壁状の構造物等で、構造物の⻑⼿⽅向にある間隔で断⾯⽋損部を設け、その箇所にひび割れを誘発させる⽅法。一般的には、誘発目地の間隔は、コンクリート部材の高さの1~2倍程度とし、その断⾯欠損率は50%程度以上とすることで確実に誘発できる場合が多い。
□ パイプクーリング
マスコンクリートの温度ひび割れ対策として⼤規模ダムなどで使⽤される。コンクリート中に埋め込まれたパイプに冷却⽔や河川⽔などを通⽔する事によりコンクリートの上昇温度を⼩さくし温度ひび割れを抑制する⽅法。パイプには外径25mm程度の薄⾁鋼管(SGP管など)が⽤いられる事が多い。
□ プレクーリング
液体窒素や冷水、氷などであらかじめコンクリート材料(骨材や水など)を冷却し打設前のコンクリート温度を低くする事によりその後の温度上昇量を小さくする方法。ミキサー内部に液体窒素を直接吹き込む場合もある。
□ 内部拘束ひび割れ
コンクリートの表面と内部の温度差から生じる内部拘束作用によって発生する応力により、初期の段階に発生する表面ひび割れ
□ 線形累積損傷則(マイナー則)
疲労による劣化進行の予測をする方法のひとつ。累積疲労度Mの値が1を超えると予測される場合には、加速期あるいは劣化期の過程にあると判定することができる。
M=Σj(nj/Nj)
M:累積疲労度
nj:作用応力振幅⊿σjの繰り返し回数
Nj:作用応力振幅⊿σjによる疲労寿命
M=Σj(nj/Nj)
M:累積疲労度
nj:作用応力振幅⊿σjの繰り返し回数
Nj:作用応力振幅⊿σjによる疲労寿命
□ 疲労強度
繰り返し応力によりコンクリートが破壊される限界の強度。
□ ペシマム現象
アルカリシリカ反応において、反応性骨材と非反応性骨材の両者の混合比が、ある特定の値の場合にアルカリシリカ反応を最も促進させ膨張量が最大となる現象。
□ アルカリ総量
アルカリ総量の計算方法はJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書6(規定)「セメントの選定等によるアルカリ骨材反応の抑制対策の方法」に定められている。
Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp+Rr
Rt:コンクリート中のアルカリ総量(kg /m3)
Rc:コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Ra:コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rs:コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rm:コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rp:コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rr:コンクリート中の安定剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp+Rr
Rt:コンクリート中のアルカリ総量(kg /m3)
Rc:コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Ra:コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rs:コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rm:コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rp:コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
Rr:コンクリート中の安定剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
□ クリープ係数
クリープひずみの弾性ひずみに対する比率
クリープ係数φ=εc/εe
εc:クリープひずみ εe:弾性ひずみ
クリープ係数φ=εc/εe
εc:クリープひずみ εe:弾性ひずみ
□ クリープ
持続荷重が作用した時、時間の経過とともにひずみが増大する現象
まず、載荷時に弾性ひずみを⽣じ、時間が経過するとクリープひずみを⽣じる。そして、ある時間後に除荷すると除荷時の弾性ひずみが生じ、時間とともに回復クリープひずみが⽣じる。最終的には⾮回復クリープひずみが残る。
まず、載荷時に弾性ひずみを⽣じ、時間が経過するとクリープひずみを⽣じる。そして、ある時間後に除荷すると除荷時の弾性ひずみが生じ、時間とともに回復クリープひずみが⽣じる。最終的には⾮回復クリープひずみが残る。
|トップページ|用語辞典|お問い合わせ|個人情報保護方針|福美ホーム|
|温度応力解析|温度応力解析事例|温度応力解析実績|温度応力解析費用|
|調査・診断| 調査・診断事例|調査・診断実績|調査・診断費用|
まずはお気軽にお問い合わせください。
福美建設 株式会社
本社
〒399-4231 長野県駒ヶ根市中沢4894-1
TEL:0265-87-2211(代) FAX:0265-87-1020
インフラ保全事業本部 技術部
担当 田口
E-mail:masscon@fukumiconst.jp
〒452-0003 愛知県清須市西枇杷島町末広77
TEL:052-325-8791 FAX:052-325-8792
本社
〒399-4231 長野県駒ヶ根市中沢4894-1
TEL:0265-87-2211(代) FAX:0265-87-1020
インフラ保全事業本部 技術部
担当 田口
E-mail:masscon@fukumiconst.jp
〒452-0003 愛知県清須市西枇杷島町末広77
TEL:052-325-8791 FAX:052-325-8792
Copyright(C):Fukumi Construction Co., Ltd. All Rights Reserved.